Previous Page · Next Page

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
2月4日はこんな日です。
銀閣寺の日、西の日(ウエストデー)、ぷよの日
◇立春
銀閣寺、高校の修学旅行で見に行った覚えが・・・。
高校生のボクは、一休さんに出てくる金閣寺は、金色なので、銀閣寺は銀色だと思ってました。
見に行ったら、じみーな感じでした。わびとかさびとか感じる年頃でもありませんでした。「日本の文化」とか、そういうものもよくわからずに、ただ、自分の思い込みと違った現実のたたずまいを見て、「面白くないなー」と思いました。
書いてみたけど、まったく盛り上がることのない、地味なエピソードでした。
読み進めると、
※【銀閣寺の日】
1482(延徳元)年、足利義政が銀閣寺(東山山荘・慈照寺)の造営に着手した。
当初、金閣寺(鹿苑寺)に倣って銀箔を貼る予定だったが、実現されなかった。
と、ありました。なんだ、ほんとに貼る予定はあったんですね。
「銀閣寺」のキーワードで鹿追町図書館の蔵書を検索します。
一件だけ、この日を待つようにひっそりとありました。
「銀閣寺の惨劇」吉村達也 徳間書店 1993年刊行
小説ですが、フィクションくらい派手にいきましょう。
そして、西の日でした。
※【西の日】
「に(2)し(4)」の語呂合せ。
この日に西の方へ向かうと、幸運に巡会えるとされている。
西へ行くと幸せに・・・。そうだ、京都へ行こう。
地味に銀閣寺と符合しました。
「西」で蔵書検索をしてみます。
204件ありました。
「神秘学の本(西欧の闇に息づく隠された知の全系譜)」学研
あ、好きなタイプの本でした。
「武四郎蝦夷地紀行(渡島日誌1~4西蝦夷日誌7~8)」松浦武四郎 北海道出版企画センター
明治の初期に北海道の調査に来て、150冊の記録書を残したすごい人です。
移動するだけでも大変なのに・・・。道路が整備され、自動車で動き回れる今でも、北海道中なんて見て回るのは大変なのに、明治の初めに全道を歩いたとは、大変さが想像の外です。
「勇のこと(坂本龍馬、西郷隆盛が示した変革期の生き方)」津本陽 講談社
現代も、人口減少社会の入り口で、変革期といえるかもしれません。なかなか視点を変えたり行動を変えたりするのは難しいかもしれません。が、必要なことですね。
「温泉百話 西の旅」種村季弘 筑摩書房
なにか、ホッとしそうなお話が読めそうです。
「西洋占星術(科学と魔術のあいだ)」中山茂 講談社
これも好きなジャンルの本です。
なぜ好きなのか・・・、思い起こすと、堀井雄二さんのドラゴンクエストが面白かったからですね。そこで影響を受け、ファンタジー小説、トールキンの「指輪物語」、マイケル・ムアコックのエルリックサーガ、「メルニボネの皇子」、水野良さんの「ロードス島戦記」、富士見書房の「ドラゴンマガジン」、清松みゆきさんとグループSNEの「ソード・ワールドPRG」に、どっぷり浸かったなぁ。
「指輪物語」はうちの図書館にもあります。
映画、「ロードオブザリング」の原作、というタイトルの方が「ああ、あれね」と伝わりやすいのかも。
たまに、好きな本について書いてみようかな、と思いつつ。
そして、ぷよの日でした。
?
※【ぷよの日】
株式会社セガが国民的な人気ゲーム「ぷよぷよ」シリーズのPRのために制定。
2と4で「ぷよ」の語呂合わせから。
「ぷよぷよ」はやったことがあります。
「ぷよぷよ」で蔵書検索をしてみます。
0件でした。
まあ、そんな気はしました。
今日はこの辺りで。
午前10時から午後6時まで開館です。気になりましたらぜひ。

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
2月3日はこんな日です。
大岡越前の日、ジュディ・オングの日、節分、まめまき、のり巻きの日、絵手紙の日、乳酸菌の日
今日は、大岡越前の日です。
へー、そんな日があるんだー。
大岡越前といえば、大岡裁きだよなー。
そういえば最近テレビで時代劇やらないよなー。
なんて、気軽に田中さんのメルマガを読み進めたんですよ。
すると、今年一番の衝撃が走りました。
※【大岡越前の日】
1717(享保2)年、大岡越前守忠相が南町奉行に就任した。
ふむふむ。
「大岡裁き」と呼ばれる名裁判で有名であるが、19年間の在任中の裁判は3回だけで、
そのうち忠相が執り行ったのは1回だけだった。
えー! そうなのー! 三方一両損とか、二人の女が「自分の子どもよ」と子どもの手を引っ張り合って子どもが「痛い痛い」とか、すくなくともどちらかの話はなかったってこと?
ショックです。
このショックは・・・、あの時以来。そう、子どもの頃、アニメ「一休さん」を毎日夕方五時ごろから見ていて、一休さんが好きになったボク。図書館でちょっと難しめの一休法師の本を見つけて、読むと、そこには、
壮年になった一休法師に、町の人がお正月に「あけましておめでとうございます」とあいさつをすると、「何がめでたいものか、年をとるということは、死に近づくということ。めでたくなんかないわ」と、とんちが効きすぎてひねくれ爺さんになっていたというエピソードがありました。アニメのイメージと違い過ぎて、このショックで、幼いボクまでひねくれてしまいました。
あと、最近話題の本を買ったら、いろいろ実在の人物が自分の名ぜりふで登場しているマンガと、文章が交互に載っている本でした。
主人公が仕事に悩んで歩いていると、ふと目についた喫茶店。そこのマスターに勧められたナポリタンを食べながら、マスターとの会話で仕事のヒントをもらったというエピソードがありました。
そのマスター、坪井さんは実在の人物なのです。でも、坪井さん自体は喫茶店のマスターをやったことがなかったということが本人のブログで明らかになっています。
坪井さんもこの本も知らない人には説明しがたいのですが、これもプチ衝撃でした。衝撃でもないか。
伝わってますか?
何が言いたいか自分でもわからなくなってきたので、本を探しましょう。
「大岡」で鹿追町図書館の蔵書を検索します。
4冊ありました。
「大岡越前守」堀和久 講談社
「大岡越前」吉川栄治 講談社
正しいエピソードが明らかになるのでしょうか。
「大岡昇平(群像日本の作家)」金井恵美子 小学館
「上大岡トメの常識のアナをふさげ!!(『私ってヒジョーシキ!?』そう思ったときに読みたいトメ流40のヒント)」上大岡トメ 主婦の友社
こちらは大岡越前の本ではないですし、最後の本だけテンションが違うなと思いました。
あ、大岡越前について、メルマガの続きがありました。
しかし、いろは組町火消しの創設、小石川養生所の建設、通貨統一などを成し遂げた、
江戸時代を代表する有能な行政官であった。
8代将軍吉宗の信頼が厚く、享保の改革に協力した。
良かったー。危うく、どんな人だかわからない感じて終わるところだったけど、すごい人だった。
そして、絵手紙の日でした。
「絵手紙」で蔵書検索。
17件ありました。
「小ちゃな金メダル物語(絵手紙世界展作品集)」
「季節の絵手紙彩るやさしい消しゴム印入門」上村旺司 日貿出版社
「心のこもった絵手紙」小池恭子 フレーベル館
「そこが知りたい絵手紙質問箱」花城祐子 マール社
「心をつなぐ愛の絵手紙(第三回がまごおり絵手紙大賞)」愛知県蒲郡市 日刊工業新聞社
「絵手紙入門」小池邦夫 日貿出版社
「花の絵手紙入門」尾見七重 日貿出版社
「初心者のための絵手紙講座」小池恭子 日貿出版社
「戦場から妻への絵手紙(前田美千雄追悼画文集)」前田美千雄 講談社
「心を贈る絵手紙の本(ヘタでいい、ヘタがいい)」小池邦夫 祥伝社
「絵手紙ズウさんの痛快・駅前探見」渡辺俊博 北海道新聞社
「絵手紙365日作品集(初めての人でもすぐかける)」辰巳出版
「笑顔をはこぶ花の絵手紙」小池邦夫 小学館
「もっと楽しむ私の絵手紙(基本のおさらいから絵手紙小物づくりまで)」辰巳出版
「心をつむぐはじめての四季の絵手紙」小池邦夫 パッチワーク通信社
「戦地から愛のメッセージ(400の絵手紙にこめられた家族の絆、平和の尊さ)」伊藤半次 文芸社
「季節の絵手紙」寺西恵理子 汐文社
絵手紙、もらったら嬉しいですよね。絵手紙の得意な方が頭に浮かび、17冊全部紹介してみました。
今日はこの辺りで。
午前10時から午後6時まで開館です。気になりましたらぜひ。

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
2月2日はこんな日です。
国際航空業務再開の日、バスガールの日、頭痛の日、交番設置記念日、夫婦の日、ストレッチパンツの日、
2連ヨーグルトの日、おじいさんの日、おんぶの日、麩の日、情報セキュリティの日
今日気になったのは、この日。
※【交番設置記念日】
1881(明治14)年、1つの警察署の管内に7つの交番を設置することが定められた。
町の中に交番の建物を置き、そこを中心に制服の警察官が活動するという交番の制度は、
1874(明治7)年に東京警視庁が設置した「交番所」が世界初のものだった。
当初は、建物はなく、街中の交差点等に警察署から警察官が出向いていたが、
1881年より常設の建物を建てて警官が常駐する現在のような制度になった。
1888(明治21)年10月に全国で「派出所」「駐在所」という名称に統一されたが、
「交番」という呼び名が定着し、国際的にも通用する言葉になっているということから、
1994(平成6)年11月1日に「交番」を正式名称とすることになった。
最初は、かわりばんこに警察官が見に行く、「場所」だったので、「交番」。そのあと、建物を建てて「駐在所」。なるほど、そういうことだったのですね。
「交番」で鹿追町図書館の蔵書を検索します。
1件ありました。
「駆けこみ交番」乃南アサ 新潮社 2005年刊行
タイトルだけでは内容はわかりませんが、たぶん一度は誰かが交番に駆け込む話です。
「頭痛」で蔵書検索します。
6件ありました。
「痛みのレディスクリニック(生理痛・頭痛とじょうずにつきあう)」上坊敏子 講談社
「ようこそ頭痛外来へ」北見公一 青海社
「首をチェックして原因不明の頭痛、不調を治す」松井孝嘉 講談社
「頭痛女子のトリセツ」清水俊彦 マガジンハウス
「脳は悲鳴を上げている(頭痛、めまい、耳鳴り、不眠は『脳過敏症候群』が原因だった!?)」清水俊彦 講談社
「片頭痛の治し方(お医者さんにも読ませたい)」後藤日出夫 健康ジャーナル社
ボクも時々頭痛に襲われますが、読んでみようかな。
そして、バスガールの日なので「バス」で蔵書検索。
184件あります。
「お風呂の達人(バスクリン社員が教える究極の入浴術)」石川泰弘 草思社
たまには、こっちのバスを。
「バスガール」は、何といってもこちら。
「『はとバス』六十年(昭和、平成の東京を走る)」中野晴行 祥伝社
一度、乗ってみたいなー。
そして、バスと言えば、何度でもおススメしたいこちら。
「黄色いバスの奇跡(十勝バスの再生物語)」吉田理宏 総合法令出版
好きな本です。
今日はこの辺りで。
午前10時から午後6時まで開館です。気になりましたらぜひ。
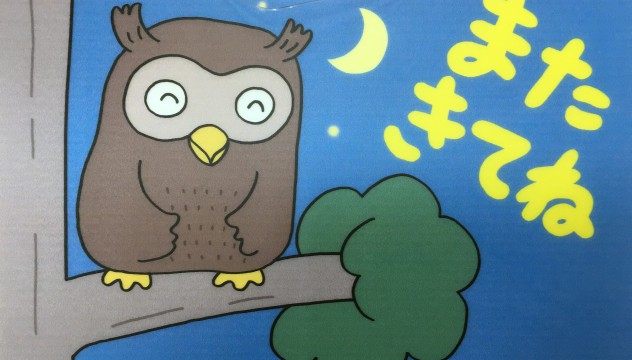
おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
ただ、ブログを書くのに日々、ネタ切れと戦っている方も多いですよね。ボクは人のお力を借りることにしています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
2月1日はこんな日です。
テレビ放送記念日、京都市電開業記念日、ニオイの日、LG21の日、ガーナチョコレートの日
琉球王国建国記念の日、プロ野球キャンプイン、二月礼者、重ね正月、一夜正月
省エネルギーの日(毎月)、安全衛生総点検日(毎月)、家庭塗料の日(毎月)、
水天の縁日(毎月1日,5日,15日)、妙見の縁日(毎月1日,15日)、資格チャレンジの日(毎月)
昭和28年のこの日、日本で初めてテレビの放送が始まったということでした。
「テレビ」のキーワードで鹿追町図書館の蔵書を検索します。
197件ありました。さすがですね。
いくつか紹介します。
「ニッポンのテレビドラマ21の名セリフ」中町綾子 弘文堂 2007年刊行
テレビドラマから、21個だけ名セリフを選ぶと、いったいどれになるのか、気になります。
「ゲゲゲの女房(NHK連続テレビ小説)」武良布枝/原案 日本放送出版協会
水木しげるさんの奥さんで話題になったNHKのドラマですね。
「テレビの企画書(新番組はどうやって生まれるか?)」栗原美和子 ポプラ社 2015年刊行
「ドラえもんひみつじてん(テレビ超ひゃっか)」藤子・F・不二雄/原案 小学館 2011年刊行
ドラえもん、なつかしいなぁ。ボクも小さいころ、親にねだって「ドラえもんひみつ道具大百科」(タイトルは正しいかどうか、こんな感じの記憶)を買ってもらって、ボロボロになるまで読みました。捨てちゃったかなぁ。
「テレビ放送のひみつ」藤みき生 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 2012年刊行
学研のひみつシリーズは、ちびっ子が借りてくれるとボクも嬉しくなる本です。
今日はこの辺りで。
本日は休館日ですので、火曜日以降、またよろしくお願いします!

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
ただ、ブログを書くのに日々、ネタ切れと戦っている方も多いですよね。ボクは人のお力を借りることにしています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
1月31日はこんな日です。
生命保険の日、愛妻家の日、愛菜の日、防災農地の日、晦日正月、晦日節、
そばの日(毎月最終日)
愛妻家の日・・・。残念ながら、奥さんがいないので関係なかった。
そばの日でした。毎月、最終日はそばの日なのですね。昨日食べちゃったな。
そして、生命保険の日でした。
生命保険、ボクも入っていますが、正直なんだかよくわかっていないです。あんな細かい字の契約書、読まないですよね。たぶん、いいお客さんなんだろうなぁ。でも、入らないと不安だしね。うーん、ちょっと勉強してみますか。
「生命保険」で鹿追町図書館の蔵書検索をします。
8件ありました。粒ぞろいです。タイトルを並べてみます。
「これからの生命保険(安心して契約するために)」安井信夫 中央公論新社 2000年刊行
「生命保険はだれのものか(消費者が知るべきこと、業界が正すべきこと)」出口治明 ダイヤモンド社 2008年刊行
「こんな時、あなたの保険はおりるのか?(生命保険から、自動車保険、レジャーの保険まで充実のQ&A85問)」清水香 ダイヤモンド社 2006年刊行
「生命保険のカラクリ」岩瀬大輔 文芸春秋 2009年刊行
「図解本当に得する生命保険選び方・使い方がわかる本」エフピーウーマン 成美堂出版 2010年刊行
「ムダをなくしてお金をタメる生命保険活用術」八百坂峰穂 池田書店 2013年刊行
「生命保険にだまされるな!」横川由理 宝島社 2014年刊行
「『安いだけ』の生命保険はやめなさい! (保険会社の社員が客に読ませたくない『おそろしい保険の話』)」三田村京 自由国民社 2014年刊行
まさに、お客の立場で読んでおくべき本がそろっています。今日の本は、タイトルに力がありますねー。
「生活とお財布を守る!」 特集として、本棚とは別に並べてみても活躍してくれそうな本たちですね。
図書館の棚には、役に立つ本がいっぱい並んでいます。多くの人に読んでもらえるように、少しでもお役に立てればと思いつつ、今日はこの辺りで。
昨日から、鹿追町図書館では保存期限の過ぎた雑誌や、蔵書スペースや貸し出し回数の関係で泣く泣くお別れせざるを得ない本たちを里子に出しています。
それをうちの図書館では『雑誌還元』と呼んでいますが、このイベント名だけ聞いても分からないから親しみやすいネーミングを考えてみないとね。
伝わりやすいネーミングのための本もあるし(家にだけど)。
そんなわけで、本日、午前10時より午後6時まで開館です。お時間がありましたら、ぜひ!

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
ただ、ブログを書くのに日々、ネタ切れと戦っている方も多いですよね。ボクは人のお力を借りることにしています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
1月30日はこんな日です。
3分間電話の日、
みその日(毎月)
3分間電話の日、
みその日(毎月)
むむむ、今日は少ないですね。でも、電話のキーワードならいっぱい本がありそうです。
あ、なぜ三分間電話の日かというと、市内通話料金が三分十円になった日が今日だということでした。
若い人にはピンと来ないかな。公衆電話(まず、これがわからないか・・・)に10円入れて、ダイヤルを回して(これもわからないか・・・)相手先につながって、3分経ったらブツっと切れる。切れる前にブザーか何か鳴ったような気もするけど、ボクももうあまり思い出せないや・・・。
「電話」で鹿追町図書館の蔵書を検索します。
何度か、このタイトルで検索しているような気はしますが、まあいいや。
32件ありました。
「電話の応対(上司や先輩がおどろくほど、上手な電話のかけ方・受け方)」浦野啓子 PHP研究所
「臨機応変!! 電話のマナー完璧マニュアル」関根健夫 大和出版
「電話応対のマナー120のシーン別正しい受け答え(そのまま使える実例集)」大嶋利佳 秀和システム
このあたりを押さえておけば、ビジネスの電話はバッチリです。
あと、書棚で見て気になっていた一冊。
「校長、お電話です!」佐川光晴 双葉社
校長先生が電話に出ると、相手はいったいどんな話を始めたのか?
なんだかトラブルの予感がするのは、ボクがネガティブだからでしょうか。いい電話の雰囲気がしないんですよね。不思議と。
毎月30日は、みその日でした。
「みそ」で蔵書検索。
19件ありました。
今日はこの一冊。
「みそのひみつ」大岩ピュン 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室
学研のひみつシリーズです。確かに、みそについて知らないことだらけでした。
この間、友達に送ってもらった「家庭でできるみその作り方」のレシピをもう一度見てみよう、と思いながら今日はこの辺りで。
本日、午前10時より午後6時まで開館です。お時間がありましたら、ぜひ!

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
ただ、ブログを書くのに日々、ネタ切れと戦っている方も多いですよね。ボクは人のお力を借りることにしています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
1月29日はこんな日です。
世界救らいの日、人口調査記念日、南極の日、昭和基地開設記念日、タウン情報の日
肉の日(毎月)、クレープの日(毎月)
ハンセン病の患者さんが、法律で強制的に隔離されていた時期があります。その「らい予防法」は平成8年まであったそうです。以前は不治の病でしたが、現在は医学の発展により薬で完治できるようになったが、まだ誤解や偏見が残っているとのことでした。一度出た情報は、インパクトが強いと間違っていたとしても、なかなか訂正が浸透しないですよね。
「ハンセン病」で鹿追町図書館の蔵書を検索します。
3件ありました。
「ハンセン病療養所(冬敏之短篇小説集)」冬敏之 壺中庵書房
「ばらの心は海をわたった(ハンセン病との長いたたかい)」岡本文良 PHP研究所
「神谷恵美子(ハンセン病と歩んだ命の道程)」大谷美和子 くもん出版
タイトルからも、読むと心が揺さぶられるであろうことが推測されます。
続いて、田中さんのメルマガから、引用します。
※【人口調査記念日】
1872(明治5)年、日本初の全国戸籍調査が行われた。
当時の人口は男1679万6158人、女1631万4667人で合計3311万825人だった。
なるほど、およそ140年前は日本の人口は3300万人ほどだったということでした。それから、ずいぶん増えましたね。これから人口が減っていくとのことで、各地でその変化への対応が問われています。
「人口」で蔵書検索をしてみます。
16件ありました。
気になるタイトルが、あれこれ出てきました。
「文明の人口史(人類と環境との衝突、一万年史)」湯浅赳男 新評論 1999年刊行
「人口減少の経済学(少子高齢化がニッポンを救う!)」原田泰 PHP研究所 2001年刊行
「人口ピラミッドがひっくり返るとき(高齢化社会の経済新ルール)」ポール・ウォレス 草思社 2001年刊行
おおよそ15年前の本ですが、逆にこの時期から人口減少はわかっていたことで、その対策が進んだかどうか確認の意味でも、今読んでみるのもありだと思います。
新しめのこちらも。
「日本人はどこまで減るか(人口減少社会のパラダイム・シフト)」古田隆彦 幻冬舎 2008年刊行
パラダイム・シフト・・・。モノの見方の転換だったかな。
調べてみました。
「その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化することを言う。パラダイムチェンジとも言う」
つまり、こういうことでしょうか。
昔は、地球のまわりを星々が回っていると考えられていた(天動説)のが、実は地球が自転していて昼や夜が来る(地動説)、ということがわかった、というのが大きな例になりますか。
確かに、人口が増えていく時に作られた制度やシステムを、人口が減っていくのにそのままで運用していたらうまくいきませんよね。
「人口激減(移民は日本に必要である)」毛受敏浩 新潮社 20011年刊行
移民については、文化が違い、言語が違う方々とともに地域づくりをするということになると、相応の対応を準備しないと混乱して仲たがいすることになります。これについては、諸外国が移民受け入れをしてどうなっているか、きちんと調べてからの議論が必要ですね。
「人口が減り、教育レベルが落ち、仕事がなくなる日本(これから確実に起こる未来の歩き方)」山田順 PHP研究所 2014年刊行
これまた気になるタイトルです。プロの囲碁棋士がコンピューターに負ける時代です。10年したら、このブログもボクじゃなくてコンピューターが書いているかもしれません。ただでさえ、人が減る分、物も不要になり、仕事がなくなるのに加え、コンピューターに仕事を奪われる時代です。
せめて、教育レベルが落ちないよう、図書館としても手を打っていきたいところです。ささやかな一手ずつでも。
「夕張再生市長(課題先進地で見た『人口減少ニッポン』を生き抜くヒント)」鈴木直道 講談社 2014年刊行
夕張の、若い市長さんが日々、頑張っていらっしゃいます。東京都職員の立場を捨てて、夕張のために奮闘する姿から、ボクも自治体職員として学ばなければ。
今日はこの辺りで。
本日、午前10時より午後6時まで開館です。あ、金曜日なので開館延長で7時まで開いています。
お時間がありましたら、ぜひ!

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
ただ、ブログを書くのに日々、ネタ切れと戦っている方も多いですよね。ボクは人のお力を借りることにしています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
1月28日はこんな日です。
コピーライターの日、宇宙からの警告の日、衣類乾燥機の日、逸話の日、
ダンスパーティーの日、ニワトリの日(毎月)、米の日(毎月)
昭和31年のこの日、「万国著作権条約」が公布されて、そこからコピーライターの日になったそうです。
「コピー」のキーワードで鹿追町図書館の蔵書検索をしてみます。
ずばり、ありました。
「コピーライターの世界(世の中、ぜんぶ広告なのだ)」糸井重里 徳間書店 1984年刊行
およそ30年前の本ですが、このころから本を出すほどの活躍をされている糸井重里さんでした。いまだに、コピーライターと言えば糸井さんの名前が一番に浮かびます。すごいなぁ。
「ひらがな・カタカナ21書体(コピーして使えるPOP広告書体)」古川貢 マール社
書体の練習をして、いろんな本をPOPで紹介したいなぁ。
「コピー用紙で折る(『白のおりがみ』で、名人技にチャレンジ!)」笠原邦彦 日貿出版社
これは、地味にいつか役に立ちそうな技術です。
※【宇宙からの警告の日】
1986(昭和61)年、アメリカのスペースシャトル・チャレンジャーが打ち上げられ、
発射74秒後に爆発し、乗組員7人全員が死亡した。
作家・大江健三郎は『治療塔』の中でこの事故を「宇宙意志からの警告」と表現した。
チャレンジャーの事故は、子どものころ、ニュース映像で観た記憶がありますが、あまりよくわかってなかったなぁ。
※【逸話の日】
まだ世の中にはあまり知られていない興味深い話(逸話)を語り合う日。
人物や物事のエピソードから本質を探ることの大切さを知るのが目的の日。
日付は1と28で「いつわ」の語呂合わせから。
なるほど、これは楽しみです。どんな話があるのか、逸話のキーワードで蔵書検索をしてみます。
な、なんと、1件でした。
「日本刀ビジュアル名鑑(写真と逸話でより深く日本刀を学ぶ)」かみゆ歴史編集部 広済堂出版 2015年刊行
激的に渋い一冊が現れました。日本刀にまつわる逸話。これを読めば教養アップ間違いなしですね。
NHKのニュースを見ていたら、ショッキングなニュースが
。ついに、コンピュータが人間のプロ棋士に囲碁で勝利してしまったとのこと。チェス、オセロ、将棋に続いて、一番複雑でまだまだ人間は負けないと言われていた囲碁が、負けてしまいました。ショックだなぁ。そのソフトを開発したのはグーグルとのこと。グーグルが開発した検索エンジンや、マップアプリなど毎日便利に使ってますが、ちょっと恐ろしい気もするのは、手塚治虫さんの火の鳥未来編で読んだ、世の中をつかさどるマザーコンピューターの暴走で世界が滅びた恐怖のエピソードが脳裏に浮かぶボクだけでしょうか。
あ、手塚治虫さんの名作、火の鳥も鹿追町図書館で貸し出ししています。奥の書庫にあるので、スタッフに声をかけてくださいね。
今日はこの辺りで。
本日、午前10時より午後6時まで開館です。お時間がありましたら、ぜひ!

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
ただ、ブログを書くのに日々、ネタ切れと戦っている方も多いですよね。ボクは人のお力を借りることにしています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
1月27日はこんな日です。
国旗制定記念日、求婚の日、ハワイ移民出発の日、
仏壇の日(毎月)、交番の日(毎月)、ツナの日(毎月)
※【国旗制定記念日】
国旗協会が制定。
1870(明治3)年、太政官布告第57号の「商船規則」で、国旗のデザインや規格が定められた。
それまでは、船によってまちまちのデザインの旗を使っていた。
当時の規格は、縦横の比率は7:10で、
日の丸が旗の中心から旗ざお側に横の長さの100分の1ずれた位置とされていたが、
現在は、1999年8月13日に公布・施行された「国旗国歌法」により、
縦横の比率は2:3、日の丸の直径は縦の長さの5分の3、
日の丸は旗の中心の位置となっている。
ふむふむ、こういう風になっているのですね。ふだんあまり考えないで目にしているけど、バランスが狂うと違和感を覚えるのかな。
今日は求婚の日でした。どんなタイトルがあるかな、と鹿追町図書館の蔵書を検索したら、
「スター・ウォーズ レイアへの求婚」デイヴ・ウルヴァートン
竹書房 1995年刊行
の上下巻がありました。今話題のスター・ウォーズです。みなさん、ご覧になりましたか? ボクはまだ見ていません・・・。
田中さんのメルマガを読み進めると、
音楽家のモーツァルトや不思議の国のアリスなどで有名なルイスキャロルの誕生日でした。
試しに、「アリス」のキーワードで蔵書検索すると、不思議の国のアリスが出てくるのですが、外国の著者の場合、「ルイス」だったり「ルイース」だったり、読み方がいろいろあります。
図書館の検索機などでお探しの作品が見つからない場合、こういうことで検索漏れの場合もありますので、スタッフに「○○探してるけど、ないのかな?」とお声がけください。見つかる場合があります。
「不思議の国のアリス」
「鏡の国のアリス」
と続きますが、
「神田日勝(北辺のリアリスト)」鈴木正実 北海道新聞社
も出てきました。きちんと、「アリス」が中に入っています。
郷土が誇る画家、神田日勝さんについては、またゆっくり書くことにして、
今日はこの辺りで。
本日、午前10時より午後6時まで開館です。お時間がありましたら、ぜひ!

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、ボクは図書館で働いています。
最近、図書館所蔵の本をブログで紹介しています。
というのは、面白そうな本でも、なかなか書棚から見つけられないんです。
あらゆるジャンルの本を収集するという使命が図書館にはあります。
当図書館所蔵の8万冊以上の本の中に、「これ、読んでみたかった!」「知らなかったけど、読んだら面白かったー」という、あなたにぴったりの本、必ずあるはずなのですが、なかなか巡り合えない。
(あ、すみません。正確には、映像資料等も含んで、「資料」というものが8万点以上、ということなのですが、ややこしいのでざっくり書いています)
少しでも、本との出会いのきっかけになれればいいな、とブログを書いてみています。
ただ、ブログを書くのに日々、ネタ切れと戦っている方も多いですよね。ボクは人のお力を借りることにしています。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めています。
以前から親交のある(とボクが思っている)田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
1月26日はこんな日です。
文化財防火デー、有料駐車場の日、パーキングメーターの日、帝銀事件の日、
オーストラリア・デー、コラーゲンの日、携帯アプリの日
ふろの日(毎月)
奈良の法隆寺にある貴重の壁画が火事になったことで、文化財を守る意識を高めようと、文化庁と消防庁が「文化財防火デー」を制定したとのことです。
文化財や郷土資料を後世に残していくのも図書館や博物館の大事な使命です。
「文化財」のキーワードで鹿追町図書館の蔵書を検索すると、34件ありました。
「もっと知ろう身近な文化財(みる ふれる したしむ)」北海道教育委員会
「民俗文化財の手びき(調査・収集・保存・活用のために)」文化庁内民俗文化財研究会 第一法規
「ふるさとの文化(北海道の国・道・市町村の指定文化財一覧)」北海道教育庁生涯学習文化課
なるほど、これは読まなければならないなぁ。
ためしに「駐車場」のキーワードで蔵書検索すると、2件ありました。あるもんだなぁ。
「自転車駐車場のひみつ」鳥飼規世 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室
ひみつシリーズ、自転車駐車場のひみつを明らかにしていますが、鹿追の自転車駐車場は建物の近くに白線が引いてあったり、引いてなかったり、あまり秘密がある雰囲気ではありません。都会はいろいろな駐車場があるのでしょうね。自分の町以外で自転車に乗ることがないので気にしたことがないなぁ。
帝銀事件、言葉だけしか聞いたことがないのですけど、田中さんのメルマガより、
※【帝銀事件の日】
1948(昭和23)年、東京・豊島の帝国銀行椎名町支店で帝銀事件が起こった。
東京都の衛生課員と名乗る男が、「近くで赤痢が発生したので予防薬を飲んでもらう」
と偽り行員16人に青酸化合物を飲ませて殺害し、現金16万円と小切手を奪って逃走した。
当初は青酸化合物の扱いに熟知した旧陸軍細菌部隊関係者を中心に捜査されていたが、
その年の8月に画家・平沢貞通を北海道小樽で逮捕、1955(昭和30)年8月に死刑が確定した。
しかし、審理に不審な点が多く、冤罪であるとしてその後何度も再審請求が出された。
平沢貞通は刑を執行されないまま1987(昭和62)年に獄中で病死したが、現在でも支援者が
名誉回復の為の再審請求を続けている。
この事件にもとに、横溝正史の『悪魔が来たりて笛を吹く』等多くの推理小説が書かれた。
これは、謎の多い事件なのですね。
横溝正史さんの作品もたくさんありますので気になりましたらぜひ。
今日はここまで。
本日、午前10時より午後6時まで開館です。お時間がありましたら、ぜひ!