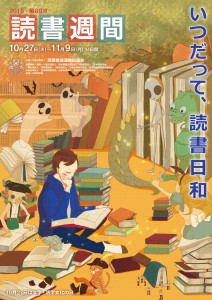Previous Page · Next Page
おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、図書館で働いています。読書離れ、活字離れで本が売れなくなっている。書店が減り、図書館からも利用者が減っているということが言われます。
ボク自身は子どものころ、図書館によく通っていました。でも、大人になると、読む時間(余裕)がなくなるのと、おこづかいがちょっと増えたので、いいなと思う本は買うので、なかなか図書館に行かないということがありました。周りの人に聞いてみたら、結構そういう人が多いみたいです。
いい本を伝えていくのと、無理のない読書習慣の作り方、図書館のうまい利用方法とかも提案していくことも大事かなぁ、と思っています。
図書館に来たら、こんなにいいことがあるよ、ということを書ければいいですね。
まずは、図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
12月7日は、こんな日です。
神戸港開港記念日、クリスマスツリーの日、国際民間航空デー、ラグビー国際試合記念日
「神戸」で鹿追町図書館の蔵書検索をします。
・・・21件ありました。
「神戸・心の復興(何がひつようなのか)」NHK神戸放送局 1999年刊行
阪神・淡路大震災は、二十年を経ても記憶に残っています。最初にニュースで見たとき、ヘリコプターから撮影された倒れた高速道路は衝撃でした。
「暗い森(神戸連続児童殺傷事件)」朝日新聞大阪社会部 1998年刊行
これも日本中に衝撃を与えた事件です。2015年の今なお、「絶歌」の取り扱いで書店や図書館で議論になりました。
「神戸新聞の100日(阪神大震災、地域ジャーナリズムの戦い)」
「震災下の『食』(神戸からの提言)」
震災からの貴重な教訓が得られます。教訓という言葉でよいのか、迷いますが・・・。
「神戸愛と殺意の街」西村京太郎
西村先生、ごぶさたしております。リストに先生の著作が現れると、それだけでなんだかうれしくなります。
「神戸殺人レクイエム」山村美紗
「神戸摩耶山殺人事件」斎藤栄
「神戸異人館恋の殺人」大谷羊太郎
「神戸殺人事件」内田康夫
ミステリーが続きます。ミステリーが多いということは、作家さんが筆を走らせたくなる刺激のある街、ということなんでしょうね。
そんな街、神戸が気になるあなたにこの本を。
「神戸」JTBパブリッシング
神戸の魅力がつまった一冊です。
うまくまとめたつもりになって、次のテーマ「クリスマスツリー」の日、ということで蔵書検索。
あるかな。あった。
「クリスマスツリー」ジュリー・サラモン
クリスマスツリーを介して出会う二人を描いた小説のようです。読んでいるとボクのようにやさぐれた心がほぐれる、地味ながらいいお話のようです。
「ねんどでミニチュア コースターに飾る季節の小物(おせち料理からクリスマスツリーまで、シーズンごとのかわいい飾りが簡単に作れる!)」
キーワードを書いておくことで検索に引っかかってきますね。どんなにいい本、中身でも、興味を持ってもらわなければ読んでもらえない。サブタイトルって大事だな、と思いました。
「マッチうりのしょうじょ(ほのおのなかにクリスマスツリー)」アンデルセン
絵本ですね。このお話は知らない人はいないと思う。けど、ほのおのなかにクリスマスツリー、と書かれると、雪の降る中凍える手でマッチを擦り、そのほのおの中に、存在しないはずの、しょうじょの憧れるツリーが映る光景を想像してしまい、せつない気分になりました。
絵本が続きます。
「ふたりのクリスマスツリー」
「ぎんいろのクリスマスツリー」
「おもいでのクリスマスツリー」
などなど、サンタさんが来る前に、子どもたちが寝る前に、お母さん、お父さんが読んであげてほしいな。しあわせな時間。
今日は月曜日なので休館日なのですが・・・、
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識があなたをお待ちしております。
気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。
おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
現在、図書館で働いています。読書離れ、活字離れで本が売れなくなっている。書店が減り、図書館からも利用者が減っているということが言われます。
ボク自身は子どものころ、図書館によく通っていました。でも、大人になると、読む時間(余裕)がなくなるのと、おこづかいがちょっと増えたので、いいなと思う本は買うので、なかなか図書館に行かないということがありました。周りの人に聞いてみたら、結構そういう人が多いみたいです。
いい本を伝えていくのと、無理のない読書習慣の作り方、図書館のうまい利用方法とかも提案していくことも大事かなぁ、と思っています。
図書館に来たら、こんなにいいことがあるよ、ということを書ければいいですね。
まずは、図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、紹介する本のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
12月6日は、こんな日です。
姉の日、音の日、シンフォニー記念日、ラジオアイソトープの日、サンタ・クロース・デー
手巻きロールケーキの日(毎月6日)、電話放送の日(毎月6日)
「姉」のキーワードで鹿追町図書館の蔵書検索をしてみます。
・・・大変です。1061件、ヒットしました。
一番上に出てきたのは、「北の本三○○」札幌市教育委員会 という本です。
なにか想像と違う感じ・・・。
次にならんでいるのは
「三角関係の超・心理」畑田国男
三角関係に姉が入ってくると、いろいろ考えてしまいますね。
「三万年の氏の教え(チベット『死者の書』の世界)」中沢新一
これも意味合いが違うけど、いろいろ深そうな本です。
「川端康成・三島由紀夫往復書簡」川端康成
文豪同士のやりとり、どんなことがあったのでしょう。二人の関係は不勉強でよくわからないのですが、フランクな友人同士のやりとりか、はたまたお互いの文化的な立場を意識した鎬を削るような文章や表現が並ぶのか、想像がつきません。読めばわかるんですけどね。
「冠婚葬祭の事典」三省堂編修所
北海道は、開拓の為に各地から集まってきた移民が多いので、結婚式が会費制だったり、まあ、結果的に合理的と言えば合理的な土地柄なので、他の地域の冠婚葬祭に出るときは勉強しておく必要がありそうです。本州では、お通夜は礼服ではないと聞いたことがあるのですが、はたして・・・。
リストを見ていくと、
「三毛猫ホームズの推理」
「三毛猫ホームズの怪談」
「三毛猫ホームズの四季」
と、赤川次郎さんのシリーズが続きます。「姉」で検索しているのに三姉妹探偵団シリーズより先にホームズが出てくるのはなぜなのか。
よくわからないまま、「音の日」でもあるので、今度は「音」のキーワードで蔵書検索します。
415件がヒット。これまた多いですね。
「寂聴観音経(愛とは)」瀬戸内寂聴 1990年刊行
テレビなどでもお姿を目にすることが多い、瀬戸内さんの著書です。
「幼児と音楽」音楽之友社
「子どものための音あそび集(ガラクタ楽器の世界)」音楽之友社
保育士さんにもおすすめ、かな。
「モニカ(音楽家の夢・小説家の物語)」坂本龍一・村上龍
名だたるお二人の合作らしいです。
「不安な録音機」阿刀田高
気になるタイトルです。面白そう。阿刀田さんの話、好きです。あまり読めてないけど。
「いつも音楽があった」倉本聰
倉本さんも音楽について書いていました。せっかくの音の日、読んでみようかな。
「ノックの音が」星新一
この一言で、いろんな想像をしてしまいます。名タイトル。
「音更町議会史」1990年刊行
あ、そういえば音がつきますよね。北海道以外の方が読んでくれていたら難読地名かもしれません。「おとふけちょう」と読みます。
あ、もしかして・・・。鹿追町は「しかおいちょう」と読みます。念のため。
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識があなたをお待ちしております。
気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。
おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
9月1日から図書館で働いています。何かみなさんのお役に立てることをしなくては、と思っております。
図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、今日のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
10月15日は、こんな日です。
きのこの日、たすけあいの日、人形の日、女人禁制破りの日、すき焼き通の日、
グレゴリオ暦制定記念日、ぞうりの日、赤十字デー、
イチゴの日(毎月)、お菓子の日(毎月)
早速「きのこ」で蔵書検索してみます。
58件ありました。
思ったより充実しています。
「きのこの絵本」
ふむふむ。
「きのこ(野外ハンドブック)」今関六也
「原色北海道のきのこ図鑑」仁和田久雄
「北海道のきのこと山菜(その見分け方・食べ方)」村田義一
「きのこの見分け方(野草実用図鑑)」松田一郎
「きのこ(カラー版)」清水大典
「原色 きのこ」清水大典
「きのこ(食用きのこ・毒きのこがすぐわかる)」小宮山勝司
「きのこ狩りの極意書(自然観察図鑑)」生出智哉
「日本のきのこ(山菜カラー名鑑)」今関六也
「北海道山菜・きのこ料理の本」兵藤恭子
「北海道きのこ図鑑」高橋郁男
「きのこ狩り入門(秋の楽しみ、きのこ狩りのすべてがわかる本)」Outdoor編集部
・・・思った以上に充実していますね。
「きのこ博士入門」根田仁
ここまで読めば、立派な博士だと思います、はい。
「おぼえているよ。ママのおなかにいたときのこと」
? と思いましたが、「ときのこと」の部分がきのこのワードに引っ掛かったようです。
その理論で、
「中谷真弓のエプロンシアター!(3びきのこぶた)」
も入ってきました。なるほど。
このあと、
「3びきのこぶた」
と
「おおかみと7ひきのこやぎ」シリーズが続きます。
あ、そんななか、
「こだぬきのこいのぼり」もありました。
とりあえず、58冊、きのこ図鑑と絵本がありました。すごい。
・・・ちょっと思いついて、
「キノコ」
で蔵書検索。
「キノコ狩り必勝法」
「阿寒国立公園のキノコ」
「北海道のキノコ」
「キノコの事典」
「北海道のキノコ 続」
続いたー!
なんだか、映画の脱出もので、ラストになんとか主人公が迷宮を脱出したら、そこはまた別の迷宮の入り口だった、というようなそんな気分に朝から陥ってしまったのであります。
鹿追町図書館では、8万冊のきのこ狩りの知恵ときのこの知識とキノコ迷宮があなたをお待ちしております。
気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
9月1日から図書館で働いています。何かみなさんのお役に立てることをしなくては、と思っております。
図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、今日のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
10月14日は、こんな日です。
鉄道記念日(鉄道の日)、世界標準の日、PTA結成の日、プラレールの日、くまのプーさん原作デビューの日、
ひよ子の日(毎月14日,15日)
鉄道についてはこのあいだ書いた気がするので、
「標準」の日で蔵書検索。
「薔薇作戦(戦時標準船荒丸)」谷恒生
思いもよらない本が出てきました。小説のようです。
薔薇作戦とは・・・。
「江戸語・東京語・標準語」水原明人 講談社現代新書
なるほど。言語の時代による変遷が書かれたもののようです。
「世界標準で生きられますか」竹中平蔵 1999年刊行
世界標準が書名にあるとは思わなかったので、「標準」で検索しましたが、ありました。小泉構造改革のブレーンの一人、竹中平蔵氏の著書です。世界標準に否定的なタイトルにみえますが、それとも、「世界の平均した生活より、日本はだいぶ上でしょうから、今より生活水準を落としても暮らしていけますか。いけないでしょう。だから経済成長が必要なのです」という内容でしょうか。いずれにしても、刊行から16年経っているので、経済書については答え合わせができそうです。
「標準音楽辞典 補遺」音楽之友社
これは、音楽を学ぶ人は目を通すべきですが、楽器から入っていく人はこの本は敷居が高いでしょう。
「最新標準パソコン用語事典PC/IT完全図解 2011-2012年版」
これは仕方のないことなのですが、パソコンやインターネット関係の本はすぐ古くなってしまいますね。
「最新日本食品成分表(日本食品標準成分表2010・アミノ酸成分表2010・五訂増補脂肪酸成分表完全収載)」医歯薬出版 2011年刊行
これはパソコンほど古さを感じません。不思議。
「よくわかる情報リテラシー(標準教科書)」2013年刊行
まず、情報リテラシーがなんのことかわからなかったので、ネット上の事典、ウィキペディアで調べてみました。「情報 (information)と識字 (literacy) を合わせた言葉で、情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のことである」
情報が洪水のようにあふれる世の中で、自分に必要な情報を探し出し、うまく使う能力ということでしょうか。
「エリック・シュミット」という方を、みなさんご存知でしょうか。私もよく知らなかったのですが、「Google」は聞いたことがあると思います。
その「Google」を作った人がエリック・シュミット氏なのですが、氏はこんなことを言っていたそうです。
人類の夜明けから2003年まで生み出された情報を 現代社会は1日で生み出している
最初にこの話を聞いた時は、「ええーっ? ウソだろ?」と思いましたが、考えてみると、メール(は最近減ったかも)、ライン、ツイッター、Facebook、ブログ、YouTubeなどなど、個人からの発信もどんどん増えています。
世界中の人の発信している情報を全部足すと、そうなってしまうのですね。
情報があふれて、これまで資本力のある企業の発信、テレビ・雑誌・新聞などのマスメディアが目立っていた時代から、個人の発信している情報に触れることが多い時代になっているようです。
確かに、テレビ・雑誌・新聞はどれも以前より見られなくなっていますね。
そんな中で、わざわざこのブログを読んでいただき、ありがとうございます。
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識があなたをお待ちしております。
気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
9月1日から図書館で働いています。何かみなさんのお役に立てることをしなくては、と思っております。
図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、今日のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
10月12日は、こんな日です。
大陸発見記念日(コロンブスデー)、タマゴデー、豆乳の日 パンの日(毎月)、豆腐の日(毎月)
「大陸」で蔵書検索します。
34件ありました。
「ユーラシア大陸飲み継ぎ紀行」
何かスケールが大きいような、そうでないような。
「印度ミッドナイト・トリッパー(TOKYO発五感の亜大陸行)」
これまた中身がピンとこないタイトルです。ちょっと怪しげな予感もしますね。
「北米大陸=シェラネバダ」
「北米大陸=バッドランズ」
「北米大陸=ノースウッド」
未踏の大自然、というシリーズです。これはほんとにスケールが大きい本でしょう。
「処刑大陸(処刑捜査官シリーズ)」
このシリーズは読んだことがないのですが、かなりまずい大陸のようです。
「水神(デトル)の都(風の大陸・銀の時代)」
風の大陸シリーズですね。昔、ドラゴンマガジンで読んでいました。
「歴戦1万5000キロ(大陸縦断一号作戦従軍記)」
この作戦も知らないのですが、本格派のルポでしょう。
「ウェブ仮想社会『セカンドライフ』(ネットビジネスの新大陸)」2007年刊行
ひところ話題になりました、セカンドライフについて取り上げた本です。今はさっぱり聞かないのですが、どうなったのでしょうか。
ネットビジネスの新大陸というサブタイトルがついてますが、誰がどのくらい儲かったのでしょう。儲かってない人も、この話から良くも悪くも学ぶことはありそうです。
「汽車に揺られて10000万キロ(中国大陸、ひと月3万円の旅)」
やはり、大陸というテーマだと、旅行記を思い浮かべると思います。
「旅する南極大陸(体感的究極ガイドブック)」
これも面白そうですね。行く機会はなさそうなので、本で味わってみますか。
「北海道の空港(北の大地の全12空港 四季と絶景が迎える『エアポート大陸』)」
空港の四季と言えば、冬の北海道の屋外駐車場は、旅から戻ってきて車が埋もれていてひどい目にあいます。お気を付けください。
「コロンブス(アメリカ大陸を発見した人)」
「コロンブス(新大陸の発見者)」
大陸と言えば、これを連想する方も多いですよね。
大陸というテーマは、スケールが大きすぎてなかなか想像が難しいなぁ。
あと、「タマゴ」の日なのでそばまつりで買った北さんのところの卵で朝食をとるので今日はこの辺で。
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識があなたをお待ちしております。
気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
9月1日から図書館で働いています。何かみなさんのお役に立てることをしなくては、と思っております。
図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、今日のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
10月11日は、こんな日です。
鉄道安全確認の日、リンゴの唄の日、ウィンクの日(オクトーバーウインク)、レーシックの日、 「獣医と一緒に!」の日、鯛の日、 めんの日(毎月)
「鉄道」で蔵書検索します。
138件あります。
「世界鉄道珍道中」
これは単純に面白そうですね。たぶん日本の常識から外れたような世界の鉄道のエピソードがいろいろ読めそうです。
「幻の鉄道部隊(消えた第一○一建設隊)」
これは何でしょう。戦時中の部隊なのかそうでないのかすらわからないなぁ。さすが、「幻」ですね。
「シベリア鉄道殺人事件」西村京太郎
鉄道と言えば、この方をさしおいて他にありません。御大、今日もお世話になっております。
「鉄道員(ぽっぽや)」浅田次郎
高倉健さん主演の映画で、さらに有名になった作品です。実は観たことも読んだこともないので、ストーリー知らないんですよね・・・。
「銀河鉄道の夜」宮沢賢治
名作が続きます。こちらは小さい頃に読んだので、記憶がおぼろげです。というか、昔は、どういうことになったのか読み取れなかったのです。大人になってからまた読むと、感想が違うんだろうな。
「三陸鉄道死神が宿る」辻真先 1989年刊行
これは、やはりミステリーものでしょうか。
そんな中、この本が登場です。
「鉄道ミステリー・パズル Part1」
この本があれば、鉄道ミステリーに強くなりそうですね。時刻表トリックなども見抜けるのでは。御大あやうし。
「アリア系銀河鉄道(三月宇佐美のお茶の会)」柄刀一
これは逆にミステリーの匂いのしない鉄道ものですね。内容が読めません。そこがある意味ミステリー。
「銀河鉄道の惨劇 上・下」吉村達也
しかし銀河鉄道にもミステリーの気配が。ややこしいな。鉄道とミステリーとは切っても切れないようです。
「鉄道・バス利用のアイルランドの旅」
あ、切れた。旅の叙情にあふれる一冊です。ミステリーはないでしょう。
「北海道鉄道跡を紀行する 続」堀淳一 北海道新聞社
貴重な郷土資料につながる本です。
「十勝の国 私鉄覚え書 十勝鉄道 河西鉄道 拓殖鉄道 近畿硬券部会会誌「硬券研究」別冊」
かつて鹿追にも鉄道があり、開拓の歴史の一ページでした。郷土の史跡、高架橋跡も、ときどき見学者が訪れます。
「北海道鉄道百年」北洞孝雄 北海道新聞社
この機会に少し勉強しておきたいですね。
「高倉健とすばらしき男の世界(映画『鉄道員』)」
ぽっぽやを見た方に、ぜひ。深く楽しめます。
「定年からの鉄道ひとり旅」野田隆
定年まで勤めあげ、ローカル線で各駅停車の旅をしていると、車窓から外を眺めて若いころは見えなかった風景が見えるのでしょうね。
「世界の車窓から あこがれの鉄道旅行」
こっちもいいですね。なんだかホッとします。
「鉄道模型でつくる思い出の風景(Nゲージ・レイアウト制作入門)」
これも落ち着いた趣味ですね。
「鉄道の歴史を探る(文明開化の花形)」鹿追町郷土史研究会
おお、我が町の郷土史研究会、素晴らしい本を出していました。これは勉強せねば。
「日本の鉄道車窓絶景100選」
これも楽しそうな本ですね。
「新幹線の運転(運転士が見た鉄道の舞台裏)」
これも角度が変わって興味深いです。
「十津川警部鹿島臨海鉄道殺人ルート」西村京太郎
殺人なのになんだかタイトルを見て安心してしまうのは、十津川警部の力か御大の御業のなせる業か。
「十津川警部猫と死体はタンゴ鉄道に乗って」西村京太郎
御大、筆がのってきました。
今日はこの辺で。
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識と御大があなたをお待ちしております。
今日は鹿追そばまつり二日目。道の駅しかおい特設会場で開催です!
そばまつりのついででもいいので気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。

おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
9月1日から図書館で働いています。何かみなさんのお役に立てることをしなくては、と思っております。
図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、今日のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
10月10日は、こんな日です。
目の愛護デー、アイメイト・デー、釣りの日、缶詰の日、まぐろの日、貯金箱の日、
島の日、冷凍めんの日、世界精神保健デー、銭湯の日、肉だんごの日、トマトの日、
お好み焼の日、トレーナーの日、totoの日、空を見る日、トッポの日、萌えの日、JUJUの日
おもちの日、岡山県産桃太郎トマトの日、赤ちゃんの日、ふとんの日、
LPガス消費者保安デー(毎月)、植物油の日(毎月)、金比羅の縁日(毎月)
「目」で蔵書検索します。
500件該当しました。
これだけあると、全部は見られませんね。
ひとまず一件目。
「20世紀の瞬間(報道写真家-時代の目撃者たち)」
これは、20世紀の大事件が網羅されているような、一冊では網羅しきれないような、読んだら、「ああ、あったな、この出来事」となること請け合いの本です。
眺めるだけでも、ぜひ。
「六十歳は二度目の成人式(親、社会に変わって、自分で自分を育てる時がはじまる)」日野原重明
・・・、ちょっと考えてみたのですが、どういうことが書いてあるのか想像できませんでした。まだ、ボク自身その域に達していないのでしょう。
「心を支える仏教名言365日(日々の生き方に目標を与える提言)」
これは、毎日書くブログの種にもいいかもしれません。一年後には、仏様のような人格になれるかも。いや、そんな簡単じゃないですね。
「神なき神風(〈特攻〉五十年目の鎮魂)」
今の日本の風潮では考えられないですが、お国の為に若い少年・青年たちが命を散らしていった時代がありました。「死」や「殺」が正義になる世の中は、もう訪れないでほしいですね。
「陸軍の異端児石原莞爾(東条英機と反目した奇才の生涯)」
悲劇を繰り返さないために、歴史を学ぶ必要があります。
「特養ホームで暮らすということ(ある主婦があたたかな目で記した体験レポート)」
核家族化が進む現代、終の棲家はこちらなのかもしれません。
「ひと目でわかる犬の飼い方」
散歩の仕方とか、しつけとか、たべものとか、きちんと学んでパートナーと健やかに暮らせるように、読みましょう。
「警視庁のウラも暗闇」1988年の刊行です。
告発もののようですが、だいぶ時間も経ったのでもう闇は晴れているのではないでしょうか。
「目薬キッス」
何だろうと思ったら、秋元康さんの本でした。内容はわからないけど、納得です。
「本当の旅は二度目の旅」谷村新司
あ、谷村さんの書かれた本です。ファンの方はぜひ。
「夏目漱石全集」1~10
日本人なら、一度は読みたい。でも意外と読んでなかったりする、夏目漱石さんの全集です。ボクもまだ読んでません。はい。
「二十三年目の別れ道(はじめて明かす夫・逸見政孝の闘病秘話とそれからのこと)」逸見晴恵 1994年刊行
逸見さん、ニュースだけではなく、クイズ番組などでも活躍されていましたね。ボクも好きでした。早すぎる別れは、とても寂しかったです。
「人生の目的」五木寛之
たまにしっかり考えてみる必要がありますね。
今日はブログを書くよりそばを食べに行く方が大事なのでこの辺で。
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識があなたをお待ちしております。
さあ、今日と明日は鹿追そばまつり。道の駅しかおい特設会場で開催されます。
そばまつりのついででもいいので気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。
おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
9月1日から図書館で働いています。何かみなさんのお役に立てることをしなくては、と思っております。
図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、今日のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
10月9日は、こんな日です。
トラックの日、トクホの日、世界郵便デー 、万国郵便連合記念日、「とく子さん」の日、塾の日、道具の日、トークの日 、
クジラの日(毎月)、クレープの日(毎月)、パソコン救急の日(毎月)、パソコン検定の日(毎月)
「トラック」で蔵書検索。
「サウンドトラック」古川日出男
トラックと言えば、誰しも車を思いうかべる昨今、小説のサウンドトラックが一番に出てきました。内容はわかりませんが、興味のある方はぜひ。
「アニマルトラック&バードトラックハンドブック(の山で見つけよう動物の足跡)」
こちらもいわゆるトラックとは違いますが、トラックです。ややこしいな。
足跡のことらしいです。アウトドアの好きな方におススメです。
「トラックのすべて」
やっと正統派トラックの登場です。でも、トラックのすべてと言ってもサウンドトラックやアニマルトラックのことは載っていないと思われます。
「大型トラックにのって(ジュニア・ライブラリー)」
ちびっ子は作業機や大きな車、好きですよね。お父さん、お母さん、息子さんに借りていってあげてください。多分喜びますよ。
「ちっちゃなトラックレッドくん」みやにしたつや
絵本作家みやにしたつやさんの本です。鹿追にも来ていただいたことがあります。トラックレッドくんシリーズは4冊所蔵していますよ。
「世界郵便デー」ということで、「郵便」で蔵書検索します。
20件ありました。
「菜の花郵便局(大人と子供のための童話)」つかこうへい
つかこうへいさんの著書です。大人と子供のための童話というフレーズ、気になりますね。読んでみようかな。
「小さな郵便車」三浦綾子
これも気になる一冊。
「農民兵士の声がきこえる(7000通の軍事郵便から)」
「山の郵便配達」
・・・、「ゆうびんはいたつのおしごと」、みたいな本がならぶのかなと思っていたのですが、郵便はドラマの題材になるようですね。届いた手紙の先には必ず人がいるので、なるほど、人の思いが届くというのはドラマなのですね。
と思いきや。
「男はなぜパンツ一丁で郵便局に押し入ったのか(トンデモ裁判傍聴レポート)」
すっかり趣が変わってしまいました。服もないから仕方なく、「金を出せ」と強盗に入った男の話なのでしょうか。裁判になっていますので、やっぱり捕まったようです。パンツ一丁で逃げても目立ってしょうがないですよね。
「漂流郵便局(届け先のわからない手紙、預かります)」
このタイトルだけでさまざまなことが想像できますね。気になります。
「死なないで! (1945年真岡郵便局『九人の乙女』)」
1945年と言えば、忘れもしない終戦の年です。これは涙なしでは読めない予感。
「ドリトル先生の郵便局」ロフティング
有名なドリトル先生シリーズです。有名なのですが、ボクは読んだことがなかったです。まずいかな。
「郵便のはなし(叢書名 人間の知恵)」
これは正統派郵便の本のようですね。勉強になりそう。
「郵便局員ねこ」
郵便好きで、猫好きな方に特におすすめの本!
「郵便局のひみつ」
学研のひみつシリーズ。面白いよ!!
今日はこの辺で。
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識と郵便があなたをお待ちしております。
あと、いよいよ明日、あさって、そばまつりが10・11日に開催予定です。
そばまつりのついででもいいので気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。
おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
9月1日から図書館で働いています。何かみなさんのお役に立てることをしなくては、と思っております。
図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、今日のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
10月8日は、こんな日です。
足袋の日、そばの日、角ハイボールの日、木の日、骨と関節の日、入れ歯の日、奥歯の日、
東ハトの日、レーザーディスクの日、国立公園制定記念日、コンビニATMの日、FXの日、
プリザーブドフラワーの日、
屋根の日(毎月)、果物の日(毎月)、歯の日(毎月)、米の日(毎月8日,18日,28日)
新そばの季節です。今週末の10日・11日、道の駅しかおい特設会場でそばまつりが開催されます。
というわけで、「そば」で蔵書検索。
41件ありました。
「北のそば屋さん 続」渡辺克己 北海道新聞社
いい感じのそば屋さんが紹介されてそうです。
「贋作天保六花撰(うそばっかりえどのはなし)」
? と思いましたが、うそばっかり、の部分のそばが引っ掛かったようです。
「すぐそばの彼方」
そっちのそばではないのですが、面白そうなタイトルです。
「諸国そばの本(そばの里とうまい店250)」
各地のそばの食べ歩きなんて、できたら贅沢ですよね。なかなかできないけど、いいなぁ。
「そば(手打ち・そばつゆの技法から開店まで)」
そば好きが高じてそば屋さん、という道を歩まれる人もいますね。やはり、好きなものに取り組んでいれば、技術も向上しやすいですよね。
「日曜日に楽しむ『そば打ち』(あっ簡単、すごくおいしい。)」
いいですね。ただ、ボクは不器用なので、打つより食べに行ってしまいますが・・・。
「そば学大全(日本と世界のソバ食文化)」
そばというと、和食のイメージしかないですが、他の国の「ソバ」に当たるものはどんな雰囲気なんでしょうか。かつおだしとか、そういうものでないとソバの風味が活きないような気がしますが、慣れなのでしょうか。
「そば屋翁(ぼくは生涯そば打ちでいたい。)」高橋邦弘
この方のお店はおいしいおそばが食べられそうです。
「北のそばこだわり100店」渡辺克己 北海道新聞社
北海道内なら、食べ歩きも可能かも。やってみたいですね。
「焼きそばうえだ」さくらももこ
読んでも多分食べたくはならないと思いますが、面白さは折り紙付きです。
「そばがらじさまとまめじさま」
絵本ですね。渋いところに目をつけています。
「そばの絵本」
こちらもズバリ絵本です。どんな話かな。
「やきそばパンマンとせいぶのまち」やなせたかし
学生に大人気のやきそばパンですが、アンパンマンの仲間だったようです。多分バイキンマンも出てくるのでは。
「やきそばパンマンとこおりのじょおう」
続編も出ていました。やっぱり人気があるようです。
「やきそばパンマンとブラックサボテンマン」
よく見ると、10年以上前からやきそばパンマン、登場していたようです。ブラックサボテンマンはなんだかよくわからないですが、きっと悪いやつです。
今日はこの辺で。
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識があなたをお待ちしております。
あと、何度でも言いますが、今週はそばまつりが10・11日に開催予定です。
そばまつりのついででもいいので気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。
おはようございます。北海道十勝鹿追町の公務員、石川誠です。
9月1日から図書館で働いています。何かみなさんのお役に立てることをしなくては、と思っております。
図書館は、読書する人、時間を増やそう、ということが一つの方向性だと思うので、図書館所蔵の本を紹介していきます。
「今日は何の日?」方式で、今日のテーマを決めてみます。
田中みのるさんのメルマガによると(田中さんのホームページでも調べられます)だいたい一年365日、「何かの日」になっているそうです。
10月7日は、こんな日です。
ミステリー記念日、盗難防止の日
「ミステリー」で蔵書検索します。
402件、ありました。
検索するまでは、ミステリーが書名に入っている本はほとんどないだろう、と思っていたのですが、叢書名(シリーズ)にミステリーが入っているものが検索されました。
とても全部は紹介できないので、上位の方だけになりそうです。そんな中でも、一番上に検索されたのは、
「C62ニセコ」殺人事件(トラベル・ミステリー傑作集 Part7)
やりました!
かねてよりお世話になっている西村京太郎御大がトップに出ています。いつもありがとうございます!! なんだかとても嬉しいです。
2位から4位まで、同じく西村御大の「特急『あさま』が運ぶ殺意(トラベル・ミステリー傑作集 Part8)」が入りました。
同じ本が3冊ですね・・・。
これは、「ニセコ殺人事件」が大人気で貸し出しが相次ぎ、利用者さんがなかなか読めなかったので、その続きの「あさま」は長い何人もの返却待ちを避けるために3冊購入したのでしょうか。これも一つのミステリーかもしれません。
「骸の誘惑」雨宮町子
「霧越邸殺人事件」綾辻行人
「新世紀『謎(ミステリー)』倶楽部」篠田真由美ほか
と続きます。
その次の
「の博覧会(ミステリー)」笹沢左保ほか
不思議な書名ですが、「の」の博覧会なのでしょうか。それともデータ入力でトラブルがあったのでしょうか。これもミステリーです。
「さまよえる脳髄」逢坂剛
おどろおどろしいタイトルです。
「遠藤周作ミステリー小説集」遠藤周作
1977年の刊行ですが、こちらも有名な氏の作品、楽しめる一冊かと。
「切断」黒川博行
「エトロフ発緊急電」佐々木譲
「海は涸いていた」白河道
「どんでん返し(音で描いたミステリー)」笹沢佐保
面白そうなミステリーが続きます。そんな中で目立ったのが、この2冊。
「傑作ミステリートリック23」推理作家点心会
これを読めば大半の事件が解決してしまうかも。初心者は読まない方が楽しめると思います。
「『幽霊見たい』名所ツアー(日本全国99ミステリー・スポット)」
こういう系統も、個人的には好きです。読むだけで行かないけど。怖いから。見たくはないし。
「おまえを見ている」ヴィクトリア・ゴッティ
なにか、上の書名から続くとゾクッとしますね。
「なぜ、北海道はミステリー作家の宝庫なのか?」鷲田小弥太
そうなのですね。なぜなのでしょうか。
「真夜中のミステリー・ツアー」日本民話の会学校の怪談編集委員会
これも個人的に気になる一冊です。テレビゲームですが、「学校であった怖い話」とか、「トワイライトシンドローム」とか、大好きなので、惹かれます。
「世界の怪奇伝説博物館」天沼春樹
これも好きな系統です。
「日本の怪奇伝説博物館」高橋宏幸
こっちも読みたい。
402件目はこちら。
「未確認生物UMAと巨大生物」並木伸一郎
ネッシーとか、雪男とか、水曜スペシャルとか、好きです。
鹿追町図書館では、8万冊の知恵と知識とミステリーがあなたをお待ちしております。
あと、今週はそばまつりが10・11日に開催予定です。
そばまつりのついででもいいので気が向いたら、気軽に書棚をながめに来てくださいね(でも、図書館もいろいろ事情があるので借りてもらえると助かります)。
それでは、また。